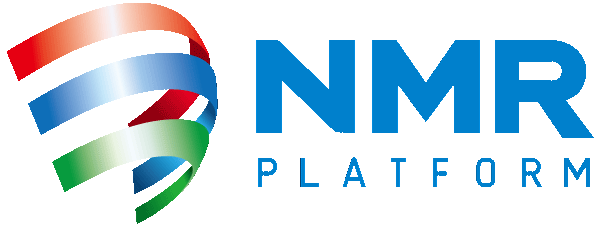安藤勲先生追悼セッション
ANDO Isao Memorial Session
2025年11月27日開催
概要
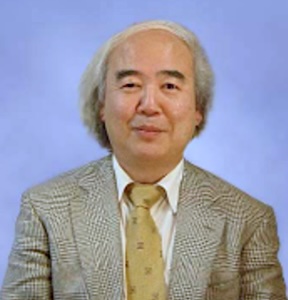
2025年2月、83歳でご逝去された 安藤勲先生(東京工業大学 名誉教授/元・日本核磁気共鳴学会 会長/ISMARフェロー)のご功績を偲び、追悼セッションを開催いたします。
固体高分解能NMRの先駆者として、ポリマー結晶の構造解析や拡散過程の研究に多大な貢献をされた安藤先生のご研究は、現代のNMR科学の基盤を築き、今なお多くの研究者に影響を与え続けています。また、東京工業大学での教育・研究活動を通じて多くの優れた人材を育成され、国際的な学術交流にも積極的に取り組まれました。
本セッションでは、安藤先生と深い関わりを持たれた研究者の皆様にご講演いただき、先生との交流やご指導、研究のエピソードを通じて、そのご功績とNMR分野への貢献の軌跡を振り返ります。
日程
ご講演者

やはり,そしてずっと勲先生の手のひらの上であった.
安藤 慎治
東京科学大学 物質理工学院・応用化学系
私は,安藤勲先生が東京工業大学の高分子工学科で独立の研究室を持たれた時(1983年)に最初に配属された4年生で,それから博士修了までの5年間,「ポリペプチド中のグリシン残基の固体13C-NMRによるコンホメーション研究」をやらせていただきました.この研究を通して学んだことは,① NMR化学シフトを含め,物理的な性質のほとんどは異方的であり,テンソル量で記述できること,また固体高分子の物性は常にその異方性を考慮しなければならないこと,② 物性の予測には量子化学計算が有効であること,そのためには理論を理解した上で,自身でプログラミングできること,③ 研究は楽天的にコツコツやっていれば,そのうち結果がついてくること,でした.後日,先生のご紹介で英国ダーラム大のR. ハリス先生の研究室に留学させていただき,固体19F-NMRによる含フッ素ポリマーの構造と運動性の研究をやらせていただきました.その後は,研究の対象が徐々に含フッ素ポリマーの構造-物性相関,中でも5G/6G無線通信や光電変換デバイスに用いられる含フッ素ポリイミドの光学物性や誘電物性に移っていき,現在はそれらが研究の中心となっています.私自身はNMR研究から離れてしまった不肖の弟子ですが,安藤研で身につけさせていただいた①~③は今もしっかり活きています.ポリイミドの屈折率(電子分極)や誘電正接(双極子分極)を解析する場合は,それらの異方性を取り込むようにしており,また実験と並行して常にDFT計算(今はGaussianを使っていますが)を流しています.月日が経つのはとても速く,来春には私も定年退職の予定ですが,研究・教育者としての約40年間,やはり,そしてずっと勲先生の「手のひらの上」であったことを,今にして実感しています.

安藤勲先生の思い出
黒子 弘道
奈良女子大学 工学部
私は安藤先生が研究室を持たれた2年目の年に4年生として配属され、修士、博士課程と進み、博士課程3年の時に安藤研の助手にさせていただきました。その後、1997年に奈良女子大学生活環境学部のアパレル科学科に赴任し、現在は4年前に新設した奈良女子大学の工学部に所属しています。研究は安藤先生と当時博士課程の学生だった山延健先生にご指導いただき、固体NMRと量子化学計算を併用した固体高分子の高次構造解析を行ってきました。このテーマは今日に至るまで続けています。追悼講演では安藤先生との思い出についてお話ししたいと思います。

核磁気遮蔽テンソルを用いた分子構造解析に魅せられて
浅川 直紀
群馬大学 大学院理工学府物質・環境部門
著者は1990年から1994年にかけて、東京工業大学・安藤勲研究室でペプチドの水素結合構造と13C磁気遮蔽テンソルの相関解析に取り組みました。最終年はワシントン大学J. Schaefer教授の研究室に留学していたため、安藤研究室での実質的な在籍は3年半でした。Herzfeld-Berger解析をペプチドの構造解析に応用した例は皆無で、先駆的な研究に高揚感を覚えた一方、ab initio計算プログラムの開発は挫折も経験しました。特に印象的だったのは、NMRとX線構造の不一致に落胆していた際、安藤先生が「X線構造の精度は高くないのでは」と語られたことで、自身の研究の意義を初めて実感しました。「方法論というのは闘いなんだよ」という先生の言葉が今も心に残っています。安藤先生のご逝去に際し、心より哀悼の意を表します。

安藤勲先生を偲び、NMR分光学への貢献を振り返る
上口 憲陽
株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター 分析センター
遡ること20年前の2005年3月19日に、安藤勲先生の最終講義が行われました。当時、私は博士課程の学生として研究室に在籍しており、「高分子NMR分光学の開発と高分子科学への展開」について熱く語られていた先生の姿が今でも思い出されます。安藤先生の主要な研究実績としては、①高分子NMR化学シフト・構造解析法の開発と高分子の高精度構造・ダイナミックスの解析、②一次元高分子、二次元高分子、三次元高分子結晶のNMR化学シフト理論の開発と高分子の構造・電子状態の評価、③高磁場勾配NMRシステムの開発と高分子ゲル・高分子液晶の拡散過程の解明、④刺激―応答NMR画像システムの開発とゲル科学への応用、などがあげられると思います。その中で、私は「高磁場勾配NMRを用いたポリメタクリル酸メチルゲル中のポリスチレンの拡散過程の研究」に取り組ませていただきました。この研究を通して、粘り強く思索と実験を繰り返し、結果の議論を楽しみながら研究を進める姿勢や、材料の構造や内部の相互作用をマルチスケールに解析することの重要性、NMRの多彩な手法がそのための強力な解析ツールになることを学びました。現在は民間のNMR研究者として、電子部品や電池材料の研究および後進の育成に携わっておりますが、研究室での学びがすべての基盤になっています。