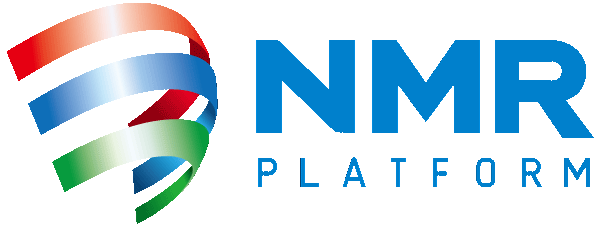チュートリアルコース
Tutorial Course
2025年11月25日開催
概要
第64回NMR討論会に先立ち、NMRの基礎から応用までを学べるチュートリアルコースを開催します。本コースは、NMR技術の理解を深めたい学生や若手研究者を対象としており、会員以外の方も参加可能です。講師には、各分野で活躍する専門家をお招きし、平易で体系的な内容でご講演いただきます。
本チュートリアルコースでは、討論会本体で予定されている招待講演者の講演内容に関連するトピックについて、基礎的な背景からご研究内容に至るまで、若手研究者にも理解しやすい形で解説いただきます。これにより、参加者はより実践的で有益な知識を得ることができ、今後の研究に役立てることができると考えております。
日程・会場
- 日程:2025年11月25日(火)午後
- 会場:沖縄科学技術大学院大学(OIST)講堂
- 住所:沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1
- 対象:学生・若手研究者
(核磁気共鳴学会会員以外も参加可能)
参加登録方法
NMR討論会に参加される方は、NMR討論会の参加登録の中からチュートリアルコースの参加希望を選択してください。
NMR討論会に参加されない方は、氏名、所属、連絡先を添えて事務局(nmr64@akane-ad.co.jp)までご連絡ください。
シャトルバスについて
恩納村内のホテルからOISTまで運行されるチュートリアルコース用のシャトルバスには定員があります。登録が遅れた場合、ご利用いただけない可能性がありますので、できるだけ早めのご登録をお願いいたします。
講師・講演内容

NMR法で捉える生体高分子の構造ダイナミクス
阪本 知樹
東京薬科大学 薬学部 分子生物物理学教室
核酸やタンパク質をはじめとする生体高分子が関与する生物学的プロセスは、それらの分子間相互作用から始まります。多くの場合、この相互作用には分子の立体配座変化が伴います。また、タンパク質や核酸はそれら自身も、平衡状態で多様な立体配座を絶えず行き来しています。この立体配座空間における構造交換の速度や各構造の存在比といったパラメータは、相互作用の強さや速度を左右し、最終的に分子の生物学的機能を決定づける鍵となります。したがって、生命現象を深く理解するためには、これら生体分子が本来備える動的な性質を理解することが極めて重要です。本チュートリアルコース講演では、本会2日目(11月27日)に予定されておりますHashim M. Al-Hashimi先生の招待講演「A quantitative and predictive model of RNA cellular activity based on conformational ensembles」に先立ち、NMR法を用いた生体分子、とりわけ核酸のダイナミクス解析について、ミリ秒からマイクロ秒といった時間スケールでの構造変化を捉えるCEST法や緩和分散法などの基礎からご説明したいと思います。

核スピン超偏極―DNP入門
松木 陽
大阪大学 蛋白質研究所
NMRで仕事をするとき、どうしても低感度が問題の一つになる。感度向上にはいろんなアプローチが考えられてきたし実装されているが、スピン超偏極は大変面白いアプローチの一つである。“うまく行くと”従来NMRの数百倍の感度が得られるので、今まで絶対にNMRを取ろうなんて思わなかった試料のNMR解析ができるようになることがあるから、すごい。しかし、どんな試料についてもうまくいくわけではないから、少し知識や工夫がいる(けっこう汎く使えるようになってきてはいるが、、)。どんな分子だとうまく行くのか、どんな試料調製をするとうまく行くのか。自分の試料に応用するにはどういう試料デザインがいいか、想像できるようにお話したい。装置はどんなのが良くて、測定条件はどうすべきか、基本的な手触りが伝わればと思う。超偏極がどう生まれるか、どんな情報が取れるのか、理論的なところにも少し触れようと思う。どんな情報が取れるのか、の部分は招待講演者Songi Han先生の講演内容の理解に、多少なりとも足しになることを期待する。

NMRによる構造解析の決め手
越野 広雪
国立研究開発法人理化学研究所 環境資源科学研究センター 技術基盤部門
分子構造解析ユニット
NMRを用いて有機化合物の構造解析を行うことは、可能性のある候補構造から立体異性体などを含め一つの化合物に絞りこむ作業である。質量分析などから分子量と分子式の情報が得られていれば、候補構造をある程度絞り込めるが、分子式の情報が無い状況でNMRデータから構造情報を集め、絞り込みことは時には難解でもある。例えば、1H NMRで2.28 ppm (s)、13C NMRで30.1ppmだけの信号を与える化合物の構造を推定する場合に、分子式の情報は必須と思えるほどであろう。ちなみに文献によるとこの測定は1H NMRはCCl4、13C NMRはC6D6のデータで、1JCH=180Hzとあるが、構造推定のヒントになるだろうか。分子式の間違った情報で構造解析を誤った事例は数多く報告されているので代表例を紹介したい。その他に構造解析を難しくする要因として、NMR信号がブロードになりスピン結合が読めないとか、相関ピークが得られないなどの理由で解析が困難になる事例も多い。測定溶媒や測定温度など、測定条件を変更することで解決できる場合もあるが、構造がまだ未決定の段階では何を変更すべきか判断は難しいことも多い。本講演ではNMRを用いて構造解析と構造訂正研究を行った中から、何が構造解析の決め手になったのか幾つかの例を紹介したい。

NMRを創った人たち:[3] Bloch と Purcell による NMR の開発 Ⅲ
寺尾 武彦
京都大学
教科書では、長年にわたって積み重ねられた多数の研究成果が系統的に整理され、簡潔に淡々と記述されていて、学問が創られた背景にある含蓄に富んだ話はすっかり削ぎ落とされている。しかし、未踏の地に道を切り開いた開拓者たちが歴史的な研究に取り掛かったきっかけや鍵となるアイデアの着想の経緯、あるいは回り道やつまずきなど創造の過程で辿った軌跡を知ることは、我々にとって間違いなく貴重な財産になるだろう。そのためには、研究を行なった本人の育った環境や受けた教育、研究が行なわれた時代背景、研究環境、周辺の人々の関わりや反応など、学問が創られるに至った状況を多面的に知ることもきわめて重要である。本講演では、NMRの分野で時代を画した研究を行った人物にスポットを当てて、できる限りその研究が成功するに至った道のりや研究が行われた現場を、様々な文脈において蘇らせる。うまくいけば、おそらくはその人物の人間性や生き方に根ざしているであろう、研究に対する姿勢やものの考え方、奥深い想いが浮かび上がってくるかも知れない。その試みを通して、研究者として歩み出した若い人たちに “科学する” とはどういうことなのかを物語全体から感じ取ってもらえれることを願っている。今回は、Purcellの幼少期から戦時研究に入るまでを扱った後、BlochとPuecellがそれぞれ戦時研究を契機としてNMRを発案するまでを講演する予定である。